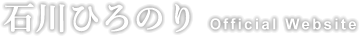石川(裕)委員 次に、オーバーツーリズム対策と持続可能な観光推進策について伺いたいと思います。我が会派の代表質問でこの点について質問させていただき、知事から答弁をいただきましたけれども、まずこの答弁の中で、観光客のマナー違反や過度の集中による影響というものがありますけれども、その規制について、まずどのようなまず状況なのかということを伺いたいと思います。
観光地域連携担当課長 まず、マナー違反につきましては、県になかなか直接住民の方からお話があるわけではないんですけれども、各地域のほうに、まず市町村含めてお話が行っているというふうに思っています。ですので、県といたしましては、例えば箱根町や鎌倉市、藤沢市のオーバーツーリズムの対策に関する協議会に参加をしたり、個別の市町村や観光協会にヒアリングをしたりいたしまして、住民の意見や課題意識について情報提供を受けている次第でございます。具体的には、特にマナー違反でいきますと、例えば鎌倉市では交通混雑のところ、それとごみやたばこのポイ捨て、それと敷地内の無断侵入、こういったようなものがマナー違反として苦情として上げられているというふうに聞いております。
石川(裕)委員 そのマナーというと、オーバーツーリズムというと、人がいっぱい来て大変だという話になる。そのマナーの啓発、ポイ捨てだとか、いろいろ前回の委員会等でも指摘させていただきましたけれども、では県として今その啓発としてどのようなことをやられているんでしょうか。
観光地域連携担当課長 県では、観光情報のウェブサイトの観光かながわNowにおきまして、ルールとかマナーを守っていただくような啓発をしております。また、外国人の観光客に対しましても、外国語の情報ウェブサイト、Tokyo Day Trip Kanagawa Travel Infoにて多言語でのマナー啓発を行っております。あとは、鎌倉市の要望に基づきまして、県のSNSで外国人観光客に向けて、11月にもマナーの啓発の投稿をしたところでございます。
石川(裕)委員 Tokyo Day Tripとかそういうものを、外国人観光客の方がじゃ実際に鎌倉に来たときにそれをどれだけ見ているのかというような、来る前はまあいろいろあるのかもしれませんけれども、じゃ実際に鎌倉に来たときに、その外国人の観光客の方がどれだけそのあれを見ているのかということはちょっと指摘をしておきますけれども、私は前回の委員会で、去年の委員会でもどこかで指摘させていただきましたけれども、京都に観光、オーバーツーリズムのことを視察させていただいてお話を聞くと、いろいろSNSでのプッシュ型の通知とかをいろいろやったけれども、一番効果があったのはやっぱりガードマンを置くこと、人を置くことだというようなことを京都の方は言っていました。人を置くということはそれだけ予算がかかりますし、それは県がやることなのか、市がやることなのか、地域の商店街がやることなのか、それはそれぞれ役割があると思いますけれども、そういうことも含めてぜひ検討いただきたいと思います。
次に、御答弁の中で、鎌倉市で実施したスマートフォンの位置情報を活用した観光客の動態分析等を今年度は箱根町で行います。先ほども委員会の中で御答弁がちょっとあったのかもしれませんけれども、この鎌倉市で行った観光客動態分析の結果、具体的にどのような分散施策が有効とされたのか。それが今もう出ているのであれば、それを教えていただきたいということと、こういう御答弁になったので、それが箱根町でどのように生かされるのか、これを伺いたいと思います。
観光地域連携担当課長 鎌倉市での調査研究によりまして、かなり迷惑行為だとか混雑というのが起こっているところ、起こっていないところ、いろいろありますが、特に今回鎌倉市のところでは、小町通りや鎌倉高校駅前付近の踏切の辺り、それと大仏含めた長谷の辺り、この3か所を特に地域として絞って調査研究をいたしました。結果的に、やはりそれぞれの地域で原因も違っておりますし、対策もそれぞれ違う形でやっていかなきゃいけないなというようなところが分かってきたというところでございます。今のような情報を地元鎌倉市とかに提供いたしまして、鎌倉市の中での今後の周遊分散も含めてやっていただきますし、県としては、さらに広域での周遊分散、または先ほど御指摘いただき
ましたけれども、旅前も含めた外国人に対してのマナー啓発、こういうようなものをしっかりやっていこうというところ、それと月別、国別によって混雑といいますか、来る人たちが違っているということも分かってきていますので、それぞれの国の方々が一番多くいらっしゃる直前にプッシュ型でマナー啓発をしていく、こういうようなものにつなげていこうというふうに考えております。
石川(裕)委員 今、鎌倉の中でも三つの地域の情報を得られて、それぞれ特徴があったということでしたけれども、もしよろしければ、言える範囲で結構ですけれども、どんな特徴があるのか、その三つ。
観光地域連携担当課長 例えば小町通りであれば、皆様、委員の先生方も御存じだと思いますけれども、やはり食べ歩きの問題、それからごみの問題等あります。まずはでも文化的な認識の違いが大きいのかなというような調査研究の結果になっています。なので、なかなか交通整理員を配置しても、それだけでは済まないかなというようなところに一旦今なっております。鎌倉高校駅前のところにつきましては、時間的には午後とか夕方が観光客が多いということもありますが、そういう一時的なところをしっかりと対応していく、それからごみ問題とか、あとここの場合は当然ですが居住地の観光地化というところが課題になっていますので、委員が先ほど御指摘いただきましたように、しっかり人で警備をしていく。調査した段階ではまだ1人だけだったり、週末だけだったりしていますが、今は平日も含めて2人の警備員で対応していますので、そのような形で変わってきているなというふうに考えております。長谷のほうは、歩道が狭くて人がなかなか歩きづらいという中で、結構交通事故が懸念をされているんですが、現実的には人と車の交通事故はそれほど多くないというところ、それから商店街の方々からは、あまりオーバーツーリズムに対しての認識は高くないというような調査結果が出てきております。ただ、やはり江ノ電の乗り方の問題、それから徒歩で鎌倉に向かっていただくような流れ、こういうふうなことをいろいろ組み合わせていくことで、時間的、場所的な混雑が少しでも解消できるんではないかというふうな報告になっておりますので、このあたりも鎌倉市と協議をした形で進めているというところでございます。
石川(裕)委員 まさに県の広域行政というところ、鎌倉市が主としてやることと、県としてそういうノウハウというか蓄積を違う市町村、ほかの32市町村に対して、鎌倉市とは直接やって、それ以外の32市町村とはそれぞれそのデータを県が持った中でこういう提案をしていくということは、私はとても重要だと思いますけれども、そういう中で、今回箱根町にこれを今度やっていくと。もともと箱根町なら交通渋滞の問題が非常に言われていましたけれども、そのほかにも今バスに乗れないとかそういう問題もありますけれども、この箱根町はどういうような情報収集されようとしているのか伺います。
観光地域連携担当課長 バスに乗りづらい、またはバスの中の混雑等につきましては、既に箱根町ないしは各バス会社でもいろいろトライをしている最中というふうに聞いております。県としては、箱根町におきましては、この交通渋滞のところが一番の問題ではありますので、地元の町役場とかDMO等、ヒアリングをしっかりやっていく中で、特に湯本駅前の交通渋滞のところをいかにしていくべきかというところもありますので、交通工学の専門家の方に研究に参加していただいて、交通工学の視点からしっかりと箱根の交通実態を調査研究をしていただいて、いかにしていくべきかというふうなところに結びつけていけるように、今調査を始めたばかりでございますので、これからいろいろ確認をしていきたいというふうに考えております。
石川(裕)委員 このオーバーツーリズムの最後の質問になりますけれども、これまでもずっと、今日第5期振興計画の改定についても、いろいろ先行会派からの質疑にもありましたけれども、この件について、オーバーツーリズムの視点が弱いんじゃないかということをこれまでも指摘をさせていただきました。そういう中で、観光課なんですかね、どこなのかあれですけれども、持続可能な観光推進に向けて、これを全体的にどうやっていくんだという方針がやっぱり私は必要だと思っているんです。それで、オーバーツーリズムを含む持続可能な観光施策、ちょっと大きくなっちゃいますけれども、そういう中で具体的なロードマップとか、もしくは今後の観光業界との連携の進め方とか、まあかながわDMOがありますけれども、そういう全体的なこの方向性というんですかね、方針というんですかね、これは来年度、それから次年度、今後に向けてどのような体制とか方針なのかということを伺いたいと思います。
観光地域連携担当課長 観光協会等と地元各自治体と、いろいろな形で先ほどお話ししたような幾つかの協議会がございますので、その中でしっかりと話をしてまいりますが、観光地のマナー違反だとか混雑に対する直接的な対応については、住民とより密接な関係がある市町村の役割だというふうに考えておりますので、そことの情報交換という中でいろいろ見てまいりますが、委員おっしゃるように、そこの取組をしっかり後押しをしていくということが必要だというふうに考えております。県では、大学の連携の枠組みを活用いたしました観光分野における県内大学との連携だとか、県が持つ幅広いネットワークを生かした研究や情報収集、先ほどお話ししたようなものも含めてしっかりとやりながら、市町村との情報共有というところをやっていきます。その上で、オーバーツーリズムの課題や対応についてしっかりと観光審議会でも議論をした上で、次期観光振興計画の改定に向けて準備を進めていきたいというふうに考えております。
石川(裕)委員 ぜひオーバーツーリズム、今も困っていらっしゃる住民の方もいらっしゃると思いますので、先、先ということじゃなくて、今も含めてぜひ早め早めの対策というものを進めていただきたいということを要望して、私の質問を終わりにさせていただきます。