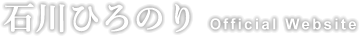石川(裕)委員 未来の石川です。早速質問に入らせていただきます。
今回、神奈川県立地球市民かながわプラザの指定管理者の選定基準について、前回は募集についてでしたけれども、今回は選定基準について報告がありましたので、この点についてまず質問させていただきます。まず、1点指摘しておきたいのは、この資料に、外部評価委員会の意見を聴取した上で次のとおり定めたので報告するという報告になっていますけれども、委員会の中でも私はこれを指摘をさせていただいていますので、これは議会からも指摘があったということをここできっちりと指摘させていただきたいと思います。
そういう中で、設備や展示機器の維持管理や修繕に対する考え方、そしてまた多文化共生や国際的理解、地球的規模の課題等に対する理解を深めるために各種企画及び展示内容の充実を図るということは理解をしましたけれども、これは今申し上げましたとおり、前回この委員会の中で様々指摘をさせていただきましたけれども、例えばモニターが古かったとか、映っていなかったとか、調整中だったとか、いろいろ指摘させていただきましたけれども、エアコンが壊れていたとかですね、その点が今どうなっているのか伺います。
国際課長 前回、いろいろと壊れている箇所の御指摘をいただいたところでございますけれども、前回調製中だったエアコンにつきましては、修理のほうも10月に終わりまして、現在はもう稼働しているところでございます。基本的には、指定管理者のほうで修理、更新などを行いまして、修理に時間がかかるもの、一部ちょっと撤去したもの等はございますけれども、そういったものを除きましてはおおむね完了いたしました。ブラウン管のテレビなど古い展示機器がございましたので、ちょっと今後は画像データを更新しやすいものに切り替えていくことを考えておりまして、今、指定管理者と更新計画を検討しているところでございます。
石川(裕)委員 私も行かせていただいて、エアコンも直っていましたし、モニターの調整中というのもなくなっていました。ただ、残念ながらブラウン管の指摘させていただいた施設のものは撤去されていました。撤去。直したんじゃなくて撤去されて、もともとじゃどういう展示物だったのかちょっと分かりませんけれども、この改修費用というのは、県だったのか指定管理者だったのか伺いたいと思います。
国際課長 今回の修繕の費用については、指定管理者のほうで負担しております。
石川(裕)委員 今回、募集ではなくて、今度は選定基準についての報告になっていますので、次回の更新に向けて、少しこの協定書というところの内容について踏み込んで確認をしてまいりたいと思いますけれども、まず指定管理者の協定書、前回も頂いて、そして今回も確認をさせていただきましたけれども、前回も指摘させていただきましたけれども、100万円という基準で、100万円以上のものは県、そして100万円未満のものは指定管理者が修繕をするというようなことになっていたと思います。それで、この修繕の、先ほども申し上げましたけれども、モニターが壊れているとか、今回もちょっと行かせてもらいましたけれども、例えば、私、全部のトイレを見たわけじゃないですけれども、この展示室があるフロアのトイレ、ちょっと見させてもらいましたけれども、男性用のトイレだけじゃないんですけれども、例えばトイレの便座とかね、それが今、普通に県庁とかもウォシュレットのああいう便座になっていますけれども、いまだに、まあ洋式にはなっていますけれども、何というか温度が、普通の古い便座で、温かくなっていないというんですかね、昔のそのままの便座になっていたりというところもあったり、あとは例えばほかの展示室の資料でいくと、例えば開発途上国の職業不足というところの展示内容があって、そのモニターの資料が2010年の世界の食料と書かれている。そして、このほかにも、世界の砂漠化というところの環境白書、1991年の資料、こういうモニターなわけですよ。こういうところが今まで変わっていなかったというところでいくと、モニターのソフトの部分ですけれども、こういうところの修繕に
関してはどうなんですか。
国際課長 常設展示室のいわゆる展示物の点検、補修であったりとか、あとデータや機器の更新、こういったことにつきましては指定管理業務としておりますので、基本的には指定管理者が行っていただくことになりますが、こういったものについては県と協議の上、実施するということになっております。
石川(裕)委員 そこなんですよ、前回の課題にさせてもらっているのは。100万円未満というところで、それは指定管理者ですよというところになっているのは理解をするんですけれども、それは結局指定管理者側が細かい修繕というものを負担していかなきゃいけないということになって、それが積み重なると、指定管理料の委託料は負担は決まっているので、年間約3億円という。となると、そういう修繕を指定管理者にお願いをしようとしても、この3億円という上限の負担がある以上は、なかなかこういうところは修繕できないわけじゃないですか。といったところで、この管理というところでいくと、もともとの持っているのは県、でも管理は指定管理者にお願いをしているというんですけれども、指定管理者はこれは悪くないですよ、きちんと使っているんだから。1991年のものだけれども。でも、こういう更新は、これは県がきちんとリードして更新していくべきじゃないんですか。そういう必要があると思うんですけれども、いかがでしょうか。
国際課長 先ほどお答えしたとおりで、現在の契約上は、展示室のデータ及び機器の更新といったところは、確かに指定管理の業務としているところでございます。一方で、開設されてから約26年というところで長い年月がたっております。古い展示物等も増えており、実際いろいろ細かい箇所の修繕等も多くなっているので、なかなか展示物の更新といったところに手が回っていないという状況もございます。次期の指定管理の募集に当たっては、今回、審査の視点として展示内容の充実というのを加えさせていただきましたけれども、これに加えて、展示の追加であったりとか展示機器の更新、データの更新とかというのも含めて、そういったところは修繕費とは別に予算を用意して計画的に改善できるよう検討しているところでございます。
石川(裕)委員 ぜひそこの修繕のところは別枠でね、本当の突発的な修繕というのは別ですけれども、そういうもう古いものとか、これまで全く変わっていないようなものに関しては、やっぱり別建てで用意してあげないと、指定管理者にそれを全て任せますとなると、これはなかなか更新が進まないと思いますので、その点はよろしくお願いします。それと、1階に、2階でしたっけ、プラザホールというところがありますけれども、まずここの管理はどこがやっているのか伺いたいと思います。
国際課長 プラザホールにつきましては、当然指定管理者が行っておりますけれども、プラザホールの運営管理については再委託という形で業務を発注しているということになっております。
石川(裕)委員 ここも私、前回もちょっと時間がなくて指摘し切れませんでしたけれども、再度今日指摘させていただきますけれども、ここに様々な外国につながる方のための書籍というものですかね、いろいろ生活に関するQ&Aとか、それに対する学校の先生に対する説明書というか、そういうものがいろいろ用意されているんですけれども、その中身を見ると、例えば「学校現場のQ&A集、(スペイン語、日本語)」、発行日が2004年3月。大阪市の「帰国した子供の教育センター校」、これが発行したのが2014年3月、そして、やっぱり神奈川県のものは何かあるのかなと思ったら、藤沢市が作っている「学校へ行こうよ」という資料があって、これが2003年1月。神奈川県教育委員会が利用している「外国につながりのある児童・生徒への指導・支援」の手引、平成24年6月。こういう資料が普通に置いてあるんです。これは管理という意味では非常によく管理されているというふうに思いますけれども、今、令和に入って、この資料がいまだに更新をされていない、変わっていない。まあ新しいものもありましたよ。でも、これじゃまず聞きますけれども、この管理というのは、この物品というのは県のものなんですか、それとも指定管理者。
国際課長 すみません、ちょっと最初に、今先生のほうからプラザホールというふうにお話あったんですけれども、こちら情報フォーラムのお話かと思います。それで、図書、書籍についてですけれども、基本的に購入した段階では指定管理者の所有となりますけれども、指定管理の期間が終了するときに、施設の継続的な運営に必要としたものについては県に無償譲渡するというふうに基本協定で定められておりますので、今買ったものについては、指定管理者のものというものもありますし、古いものは県のものということになっております。
石川(裕)委員 それで、この管理というのは、要はこの古いものがそのままあるというこの状況、こういうことについては、これは何かモニタリング調査なのか、何か外部監査なのか、県の調査なのか、これがそのまま残っている、まあ残っているというか新しいものに更新をされていないというこの点についてはどのように捉えられていますでしょうか。
国際課長 ここの情報フォーラムでは、様々な な方やその支援者、あるいは学校関係者を支援するための日本語学習資料だったりとか、そういった様々な資料を用意しておりますけれども、こういったもの、自治体等が作成したものなどは、印刷してファイルにとじたりとか、そういった作業を行って配架していたりするものも多くございます。古い情報のものにつきまして、自治体等で発行しているものについては、そもそも更新がなされていなくて残っているものであったりとか、あとは長く使われているものという可能性もあるんですけれども、委員おっしゃるとおり、恐らく本当に古いものというのが多くあろうかと思います。モニタリングというところでちょっとそこまできちんと追い切れてはいなかったというところで、改めてそういったところについても指定管理者とよく確認して対応していきたいと思います。
石川(裕)委員 他県、他市のものは からあれですけれども、神奈川県の教育委員会の資料でさえも非常に古いもの。それで、この資料をきちんと取っておくことも大事な部分はあるかもしれませんけれども、それを新しく更新することだったり、今そんなに外国の方がいらして、その本を見たりというようなものよりも、やっぱり今インターネットがこれだけ普及している中でいけば、タブレットで見られるとか、もうインターネットでこういう情報開示をするとか、そういうやり方もやはり考えていかなければいけないというふうに思いますので、その点を指摘しておきます。批判ばかりじゃいけないので、今後、来年度、この指定管理者を更新していく上で、その募集、そして選定基準も大事ですけれども、その先に、やっぱり協定を結ぶ前に、じゃ県の役割はどこまでなのか、指定管理者の役割はどこまでのなのかということを、もう26年間、今報告があったとおり、この歴史がある中で、やはりいろいろな設備の故障があるかもしれない、もしくはもう大規模にリニューアルをしなきゃいけない時期なのかもしれないというところの、募集に当たってのそういう判断がやはり必要になってくると思うんですけれども、その辺について、募集もそうですけれども、選定基準に当たって、次の指定管理者ということは30周年を迎えるようなことになると思うんですけれども、そういうときに当たって、ぜひ中身の内容のリニューアルというか、そういうことも必要かと思いますけれども、そういうお考えがあるのかどうか伺いたいと思います。
国際課長 現時点で大規模なリニューアルといったことを考えてはいないんですけれども、今回、選定基準のほうに展示内容の充実等の文言を追加したりであったりとか、我々としても展示内容については充実を図っていく必要があるということは認識しております。やはり開設後26年経過しておりますけれども、外国籍県民の方も年々増えていますし、こういった多文化共生、国際理解といった課題について、県民の方々あるいはお子様方に認識を深めていただくというのは、その役割、必要性というのは増していると思っております。ちょっと予算の関係等もありますので、大規模なリニューアルといったことについてはちょっと今後検討というところになると思いますけれども、展示の在り方につきましては、県としても今後しっかりと検討していって、次期指定管理者ともよく協議しながら、よりよい展示にしていけるよう取り組んでまいりたいと考えております。
石川(裕)委員 協議は大事です。指定管理者が決まって協議をすることは大事なんですけれども、その応募をする、これから募集をするわけですから、今、JOCAが受けている、指定管理者の事業者ですけれども、それ以外にもね、やはりこういう募集に当たっては競争が私は必要だと思うわけです。今回はいろいろ指摘させていただいていますけれども、指定管理者だけが悪いということじゃないんですけれども、やっぱり長年こうやって継続して、15年間やられてきているというところで、その長年やってきたことがもう普通になっちゃって、その状況が、今こういう状況でも、あまり分からないというか、今の状況と合っていないような、そういうところがまだ提案できなかった、そういうことも考えられますし、例えば先ほどの便座のこともそうですけれども、そういう利用者の目線に立っているというところが、前回も指摘させていただきましたけれども、ちょっと薄れてきているんじゃないかなというところが非常に感じられるというふうに思います。私が行かせていただいたときは、そのスタッフの方は非常に丁寧に説明をしていただきました。人の部分に関しては、非常に向こうからお声がけもいただいたりして、どういう目的でいらっしゃったんですかとかというようなことも聞かれましたけれども、塾の先生ですと言って回らせていただきましたけれども、そういう形で、ちょっとやっぱり議員という形になると、なかなか正直なお話もしていただけない可能性もあるので、まあそういう形でちょっとお話を聞かせていただいて、現場を ていく、状況を、お話を聞かせていただきました。そういう中で、今後この協定書、この内容というところが、私はやっぱり一つの課題になってくるというふうに思っています。先ほども申し上げましたとおり、前回5年前というか、前回のこの協定書を確認させてもらいましたけれども、これはほかの指定管理者等の協定書も同じだと、同じようなこともあると思うんですけれども、やっぱり100万円未満の費用は、100万円未満のものは乙、まあ指定管理者ですね、100万円以上のものは県が持つというような、こういうようなことであったり、先ほどみたいにいろいろ重なると100万円になるけれども、これは音楽堂にしてもいろいろ同じですけれども、重なると100万円超える。でも、1個の単体だと当然100万円未満という、こういうところのもう少し明確化というものが必要だと思うんですけれども、まあ先ほどは、修繕のところは別建てにしてもらえるということですけれども、その予算だってどれぐらいになるか分からないといったときに、もう少しここの書きっぷりというんですかね、この辺を変えることというのはできるんでしょうか。
国際課長 今の基本協定の金額というか役割分担の部分ですけれども、やはりここの部分、本当に基本となる部分でございますので、なかなか書きぶりというのは変えづらい部分かなというふうに思っております。細かい金額が例えば積み重なって修繕費がかさむというのは事実としてあると思いますけれども、そういった場合、当然ながら年度の当初に事業計画をつくりまして、各指定管理者のほうで予算立てをしています。例えば、修繕費であれば幾ら幾らというふうに予算を計上しておりまして、その中で当然やっていただくということになると考えております。なので、例えば修繕費が足りなくなるような場合であれば、そこは県と協議してその都度考えるという形になると思いますので、基本協定のところというよりは、対応できない状況が生じた場合は、協議をして合理的な手法を指定管理者と一緒に導き出していきたいというふうに考えております。
石川(裕)委員 一応まあ理解はしますけれども、次にこの管理物品のところについても、修繕は年度協定書で定める管理物件の修繕は甲ということですから県ですよね。管理物品の更新も、年度協定書で定めるというところでいくと県ですよね。先ほどの図書の話になるんですけれども、これは年度協定書では、これはどちらなんですか。
国際課長 図書については、管理物品という名目では記載していませんので、基本的には図書について購入、指定管理の業務で蔵書の収集等ございますので、指定管理者のほうで取得していただくものとなっております。
石川(裕)委員 ということで、本に関しては指定管理者のほうで取得をしてもらうというところであれば、今後そういう書籍に関しての更新についても、やはり古いものは、まあ残しておくものは残しておかなきゃいけないけれども、常に最新のものは用意しておく必要があると思うんですけれども、そういうことをきちんとやはり明確にしておく必要があると思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
国際課長 指定管理者との契約というか、資料的なものとしては、基本協定外にも、例えば業務に関する基準であったりとかほかに定めるものもございますので、そういった細かいことについてはそちらのほうにしっかり記載することで対応していきたいと考えております。
石川(裕)委員 時間がありませんので、これぐらいであれですけれども、ぜひ次、協定書の条項に具体的な基準とその運用上の柔軟性、どこまで盛り込めるのかというのはちょっと分かりませんけれども、県にしても指定管理者にしても、双方が負担を軽減して円滑な管理運営ができるような状況にして頂くことを要望して、この質問を終わります。