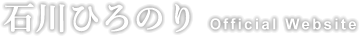石川(裕)委員 次に、県民ホールの指定管理のことについて伺ってまいりたいと思います。頂いた資料を見ると、指定管理費に関してですけれども、令和6年度の指定管理料、委託料の当初予算は、6億,803万円というふうになっています。来年度の予算案では、4月以降県民ホールが休館するにもかかわらず、約1億3,000万円の増となる約7億5,453万円となっています。令和7年度には、どのような増減が見込まれているのか、特に最大10年間、先行会派の質疑の中で、最大10年間と想定される休館期間中の管理コストとか外部委託の有無など費用の変動の要因を確認します。
文化課長 まず、令和7年度の算定についてですけれども、それぞれ指定管理料の算出につきましては、施設の運営管理や主催公演を行うため費用と、あとそれに伴う収入の見込みを算出をして、その差引きにより見積もっております。今回差引きの結果、県民ホールの指定管理料は増加しているというような状況でございます。まず、費用につきましては、県民ホールの休館に伴いまして、舞台機構の保守であると、来場者対応のスタッフ、清掃などの委託料、あと光熱水費などの施設の管理運営に係る経費が減少しておりまして、これが3億近くの減ということになっております。一方、公演の事業費ですけれども、これは県内各地で事業を実施していくということになりますので、今まで県民ホールでやっていたものが会場使用料がかかる場所で実施をするということになりますので、そのあたり。また、今まで管理運営費の中に入っていたんですけれども、例えば来場者対応のスタッフなどの経費を今回事業費という形で積ませていただいた関係もございまして、トータルで5,000万強の増加となっております。トータルで、おおよそ2億4,000万円程度の減という形に費用のほうはなっております。一方、収入に関してですけれども、基本的には今まで大ホールを貸し館という形でいろんなところに貸して、その利用料を指定管理の収入として見込んでおりましたが、これが2億円以上減しております。また、小規模な会場で実施をしますので、入場料収入などの減も見込んでおります。そうしたことから、収入のほうの減がおおよそ3億6,000万円ぐらいの減ということで見込んでおりまして、その差引きでトータル1億2,600万円の減ということで考えております。これにつきましては、令和7年度の特徴としては、施設管理がまだ残っている、休館をしますけれども建物が残っているというような、ちょっと特殊要素もございます。また、令和7年度、備品の整理を行うという業務を指定管理の中でやってもらうと、そういった業務も入っているということで、令和8年度はまた新たに見積りをしていくという形で考えております。
石川(裕)委員 いろんな数字を並べていただいて、分かるようで分からないような数字ですけれども、資料を見させていただくと、指定管理料の管理運営費というところは減っているものの、事業費が今年度は7,178万だったものが来年度は2億5,200万ということで、来年度は1億8,000万の事業費が指定管理料の中で増えているというふうに理解をしました。そういう中で、休館中の指定管理者の業務内容ですけれども、少し今触れていただきましたけれども、令和7年4月から休館に入るということで、指定管理者の業務内容が大きく変わるというふうに思われます。通常のこれまでの運営と比べて、どのような業務が増え、どのような業務が減るのか、そしてまた、休館中でも発生する固定費、維持管理費についてどのような調整を行うのか伺います。
文化課長 まず業務内容につきましては、令和7年度、公演等がなくなりますので、県民ホールの施設管理に関しては大幅に減少するものと考えております。ただ一方で、建物自体の管理とかが残りますので、一部の業務は残るというふうに考えております。一方で、今回令和7年度、新たにお願いしている業務といたしましては、備品等のトータルで管理物品と呼ばれているものだけでも4,300点ほどございますし、それ以外の消耗品なども含めますと1万点以上のものが中にありますので、そういった整理の業務は新たにお願いしておりまして、それが増加をしております。また、事業費のほうになりますけれども、今まで県民ホールでやっていたものをある意味外でやっていくということになりますので、そこの業務、業務やるという意味では変わらないんですけれども、なかなかやはり自分のところの建物でやると調整が必要なかったものが、外でやるといろんな調整が必要になってきますので、そういったところの業務が増えるものというふうに考えております。あとは、発生する業務費といたしましては、具体的には、例えば施設管理料という意味では、建物は残りますので、例えば警備費でありますとか清掃費というのは一部残ってきます、縮小はいたしますけれども。あと3館に共通してやっている、例えばチケットセンターという業務があるんですけれども、そちらは、今までずっと県民ホールの中に置いておりました。そういったものについては、令和7年度も残るというふうに考えておりますので、そういったものが令和7年度のものに計上しております。そういったところで、一方業務のほうにつきましては、今まであまりなかった、一部が外でやっているものもありますけれども、新たにやった会場の使用料、あとはリハーサルとかの場所なども新たに借りなければいけないというような業務、また経費も発生しておりますし、あと、今まで管理部の中でやっていた設備、照明とか、あとチケットのもぎりとか、そういったもののスタッフの経費もそれぞれ事業費でかかってくるという、そんな理解でおります。
石川(裕)委員 詳細に御答弁をいただきましたけれども、そういう中で、繰り返しになりますけれども、先行会派で、約10年間、一番長い形で閉館をすると、いう形でいくと、来年度は閉館するに当たっての様々な業務、備品とかの整理というのはあると思うんですけれども、それ以降、今度財団が管理するんではなくて、県が直接管理するようになるというふうに理解をしていますけれども、その辺の閉館中の固定費とか管理の維持費とか、そういうのはどういうふうに考えている。
文化課長 今の御質問、恐らく県が直営になったときに県のほうでかかる費用という御趣旨かと思いますけれども、まず先ほどの答弁でも少しありましたけれども、警備とかの経費は、全く何もしなくてもいいというわけではないと思いますので、そういったものがかかってくる可能性はあるかと思っております。あと、建物をいつ除却するかというところによると思うんですけれども、除却までの間はフェンスを置きますけれども、それに伴って何か必要なものがあれば、そういったところ、またあと、基本は電気代に関しては、街灯の部分は電気代が残るんですけれども、それはソーラーで賄うおうと考えておりますので、そこの電気代は不要かなと思っておりますので、主に警備とあと、例えば建物で何か起きたときの対処費用といいますか、そういったものは必要になるのかなと、そのように考えております。
石川(裕)委員 ということは、来年度で一定程度、施設の中のものは除去といいますか、建物はいつ除去されるか分かりませんけれども、中のものは来年度中に整理してもらうという理解をいたしました。そういう中で今度は休館中に、県内各地で、先ほど選考会でもありましたけれども、公演を実施するということでしたけれども、これらの事業に関して、これは指定管理者の神奈川芸術文化財団、そこの役割がどのように変化するのか、そしてまた会場の手配とか、演者の調整とか、広報活動の負担、これまでと比較して業務範囲がどう異なるのかということを伺います。
文化課長 神奈川芸術文化財団の業務につきましてですが、県民ホールの休館中の文化芸術事業について、主に企画であるとか、広報、集客、また実施に向けた関係者の連絡調整など、事業のプロデュースであるとか全体調整というのを担っていただこうと考えております。これも、県民ホールで実施していたときと役割が大きく変わるということでは実はないんですけれども、休館に伴いまして、例えば企画の際に会場となる市町村などの意見も取り入れた形で企画検討を進めていくであるとか、あと今まで自分のところでやっていたものの公演に関しては、会場となる施設との調整、あと広報についても今まである意味県民ホールということで一律の広報をやっておりましたけれども、地域とかターゲットに合わせた広報活動も必要となるとったことで、この間のところで新たな業務が発生をしたりとか、あとこれまでもよりも業務量が増大するのではないかと考えております。
石川(裕)委員 それだけ県内の地域に出ていくという形で、プレテストをやってもらうということでありました。この事業を見ると、事業の積算のほうを資料で頂きましたけれども、例えば、鎌倉市を含む湘南地域では、オペラ、ジャズ、クラシック、ロック、現代演劇とか7本を予定していると、来年度は。それ以外の地域では、同じように合唱だとか美術とかいろいろありますけれども、11本、公演を予定してという資料を頂いていますけれども、そういう中で、この事業において、これをいただいた中で、約2億6,700万これが支出計上されています。文化芸術活動維持と発展のために、この2億6,700万というのは使われるわけですけれども、これは、この事業の成果というのをどのように評価する。新たにこれだけ費用が県税を使って負担され、やられるわけですから、来場者数だとか参加された方の満足度とか、そういういろんな指標があると思うんですけれども、これはどのように考えているかということと、これ10年間、繰り返しになりますけれども、長期のやつ10年間になる。7年度これをやって、それ以降、これをどう反映していくのか。例えば鎌倉地域で7本が多いからここにしようとか、いろんな考え方があると思いますけれども、これをどのようにベースに考えていこうとしているのかを伺います。
文化課長 まず、事業の効果についてでございますけれども、当然事業を実施する際にはアンケートを行う予定です。先ほど委員のほうからもお話しありましたとおり、まず、どれだけ参加していただいたか、特にホールのキャパがあるものはある程度参加者数は決まりますけれども、野外でやるようなものも一部考えておりますので、そういったものについては、どれぐらい集客で来たかというのは一つの指標として挙げられるかと思います。それに合わせてアンケートを取る予定になりますので、その中でどの程度満足いただいたのか、そういったことを、アンケート内容についてじゃ今後検討しますけれども、そういったことについても調べるようにしていきたいなと考えております。令和8年度以降なんですけれども、まず重点地域については、ずっと固定ということではなくて、いろんなところをできるだけ回っていきたいなと思っておりますので、例えば鎌倉市でやったことを、そういった反省も踏まえて、例えばほかのところはこういったものをやりたいとか、地域の要望なども聞きながら、新たな事業展開というのも考えていきたいと思います。また、淡々と同じことをやっていくということではなくて、当然今回、市町村とも連携しますし、関係からもいろんな御意見も来ますので、そういったものを声を反映させながら、事業をその都度見直しながら、ただ、県民の鑑賞機会が減らないように事業は継続していきたいと、そういうように考えております。
石川(裕)委員 資料を見ますと、鎌倉市を含む湘南地域で来年度は7本というふうに計画、積算の見積りの中で書いてありますけれども、鎌倉市を含む湘南地域で7本と、例えばどんな地域でどんなことをやろうというふうに検討されているのかということと、同じく、湘南の地域外というところで11本計画をされています。この辺の、例えばどういう地域で、どういうことを、今計画の段階ですから、積算の中でどういうことをやろうとされているのか伺いたいと思います。
文化課長 今、あくまでも計画段階でこれから市町村との調整ということになりますので、積算のときのイメージというか、そういったことでお話をさせていただければと思います。まず、湘南地域に関して、鎌倉でも当然事業はやっていくんですけれども、例えば先ほどの答弁でも少し触れましたが、藤沢市は市民オペラがすごく盛んな場所になりますので、そういったところでのまずオペラ公演というのは考えていきたいなと思っております。また、少し小さなところで、例えばクラシックと朗読を組み合わせたような事業を、それはどちらかといえば小規模な市町村で実施をしたいなと思っておりますし、一部のところだとパイプオルガンの何か企画なんかもやっていければなと。ある意味、パイプオルガンというかオルガンですね、県民ホールにパイプオルガンがありましたので、そういったことを考えております。湘南以外のところについてですけれども、幾つか県央地域でありますとか、そういったところでもやりますし、例えばオペラとかも、どちらかといえば、お子様でも楽しめるような、オペラ入門編みたいなことを、それを今県央地域のほうで考えているものがございます。また、ちょっとこれは一部、平塚市と相模原市で現代演劇ということで、演劇の授業なども、これは年度当初なので、大分話が進んでいますけれども、その二つで考えているような事業がございます。
石川(裕)委員 積算で今計画の段階で、これで予算を積み上げられて、令和7年度出されてきたということは理解をしますけれども、対象となる、そういう県民ホールに代わるような施設というのは県内にそんなにあるものではないというふうに思うんですけれども、例えば、川崎市のカルッツかわさきとか、川崎市の場合幾つかありますけれども、市町村によってはそんなに大きなホールもないというふうに思いますけれども、そういう対象となる施設というのは大体どれぐらいあるんですか。
文化課長 県民ホールに近い施設ということだと、あまり正直ないかなと。それこそ川崎市に幾つかと横浜市、ちょっと用途がそれぞれまた違いますけれども、あと例えば横須賀芸術劇場であるとか、相模原市のグリーンホール相模大野が1,800ぐらいということで、今回やる際には、うまくその会場の規模にそれぞれ合わせて、もっと小規模な1,000席程度のホールでもできるようなものにダウンサイジングしてやるとか、あと極端な話、ホールがないようなところでも何か会議スペースとか、公のスペースを使って事業をやるといった、そういった工夫をしながら事業をやりたいと考えていますんで、ちょっとそういった意味では、対象は大分増えてくるのかと考えております。
石川(裕)委員 いろいろお話を聞きましたけれども、そういう中でいくと指定管理者である財団が重要な役割を担うというふうに思います。その施設運営における指定管理者、これ前回の委員会でも質疑しましたけれども、これは非公募で決まっている、財団に委託をするという形なので、新しく令和7年度県民ホールが閉館した中で、いろんな事業を進めていく、そういう中でいくと、この指定管理者に対する評価基準をどのように設定するのか。例えば、これ積み上げで18本という企画を今積算で出していただきましたけれども、例えば18本できることが基準になるのか、例えばこれがいろんな理由で15本になってしまったとか、もしくはもっと小さな事業を進めることによって30の事業になったとか、いろんなことが考えられると思うんです。そういう指定管理者に対する評価基準、これをどういうふうに変えていくのか伺います。
文化課長 評価基準、ちょっとまだ詳細に決めているわけではないんですけれども、要は、実績としてどう評価していくかということに関しては、基準を決めているわけではないんですけれども、一つは、先ほどありましたように、どれだけ多くの方に見ていただけたのか、あとはそういった企画が、例えば本数としては少ないんだけれども、関連企画みたいな形でやるというようなやり方もあると思いますので、単純に本数というだけではなくて、どれぐらいの多くの方、あとは満足度、そういったところで、県民にしっかりと届いているのかと、そういったところを総合的に評価していくのかなと、現時点ではそのように考えております。
石川(裕)委員 こういう事業ですから、やってよかったということだけでは駄目で、それが今後どのようにその地域含めて、根差していくのかとか、県民ホールでできなかったことを地域で届けていくというような、先行会派での質疑の中でもそういう御答弁がありましたけれども、届けてじゃどうだったかということが大事だと思いますので、実際地域に行ったけれども、お客様が全然来場されなかったとか、そういうことも含めて、きちんと地域に今度出ていく中での評価というものは持った形で、ぜひ事業を進めていただきたいというふうに思います。