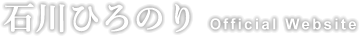石川(裕)委員 かながわ未来の石川です。早速、質問に入らせていただきます。初めに、食料品など物価高の影響を受けやすい低所得者世帯への支援、そしてまた、経済的困窮世帯に関する支援など、生活困窮者支援について伺ってまいります。まず、生活困窮者対策推進本部に関連して伺いますけれども、知事が推進本部など本部長を務める組織は現在幾つぐらいあるのか、伺いたいと思います。
総務局企画調整担当課長 現在、知事が本部長などを務めている会議体は17となってございます。
石川(裕)委員 17件も知事が本部長を兼務されていると。大変かなというふうに思ってよくよく調べてみたんですけれども、今年度、知事が本部長兼務している本部の活動があった件数は9件、そして、なかったものが8件ありました。知事が本部長でない本部を含めると、全体で33件、こういう推進本部のようなものがあると。中には、危機管理対策本部のような緊急性が高いものもある一方で、ヘルスケアニューフロンティア推進本部とか、SDGs推進本部とか、令和2年以降、会議が開催されていない推進本部もあるわけです。これは部局横断的に事業が進んでいるというふうに理解することもできるんですけれども、一方で、推進本部が形骸化しているという可能性もあるんです。そこで、各推進本部の継続、そしてまた解散の判断はどのように行っているのか、伺いたいと思います。
総務局企画調整担当課長 各推進本部などの継続、解散につきましては、各会議の事務局が本部長などを務めている知事の判断を仰いでいくものと考えます。
石川(裕)委員 解散のタイミングというのは、推進本部という中でなかなか難しいとは思うんですけれども、知事は、議会等々でも、断捨離といいますか、事業の見直しをしていくんだというようなお話もされていますので、ぜひ推進本部に関しても、こういう見直しを進めていただきたいというふうに思います。そういう中で、県は、新型コロナの影響による生活困窮者支援を充実させるため、令和3年11月に知事を本部長とする生活困窮者対策推進本部を設置しました。これまでも何度かこの推進本部について質問させていただいていますけれども、令和5年度は依然としてコロナ禍以前に状況が戻らないということで、県民を支えるためにこの推進本部を継続したと。そしてまた、今年度からは、4月施行の孤独・孤立対策推進法を踏まえて、孤独・孤立対策を中心に、より包括的な施策に推進本部が移行したと。これはホームページにも記載をされていますけれども、軸を移したというふうに理解をしていますけれども、この孤独・孤立対策関連予算を含む9億5,422万円が今年度は計上されています。この支援の軸を移したことによって、生活困窮者対策推進本部の中で事業支援内容の見直しをどのように行ったのか、伺いたいと思います。
生活困窮者対策担当課長 コロナ禍が落ち着いたことにより今年度見直した事業もありますが、生活困窮者対策推進本部の下で立ち上げた生活困窮の方へ支援する事業の多くは継続しています。今年度の本部会議におきまして、孤独・孤立対策の視点を踏まえ、人と人とのつながりを実感できる地域づくりなど取組の方向性を4本柱に整理し、庁内で共有しました。引き続きその方向性の下、推進本部を中心とした庁内連携体制により生活困窮対策の取組を進めていきます。
石川(裕)委員 事業を確認させていただくと、委員会等々でも指摘をさせてもらった介護人材、コロナ禍で介護人材の確保の進推進事業が今年度は昨年度から比較して終了した事業だというふうに理解をしています。そういう中で、一つ一つ少し確認をしてまいりますけれども、令和5年度子ども食堂応援事業協力金として1か所当たり12万円、そして198か所に総額2,376万円が支給されました。令和6年度の支給額、そして支給箇所数に変化があったのか。そしてまた、物価高騰が続いている中で、子ども食堂からどのような支援が求められているのか、伺いたいと思います。
子ども企画担当課長 令和6年度の子ども食堂応援事業協力金については、1か所当たり6万円、175か所に対して総額1,050万円を支給いたしました。子ども食堂が求める支援についてですが、県が令和6年9月から10月にかけて実施した子ども食堂活動状況調査において必要とする支援について質問したところ、財政的支援、食材の支援のほか、人材、寄贈品の保管場所、SNS等の広報などが上がっていました。
石川(裕)委員 令和5年に比べて、1か所当たりの金額は半額、12万円から6万円になったということも理解をしました。また、事業所からは、財政的支援とか食材の支援が多いということですけれども、やはり、私は行政としてはまず仕組みづくりというものが大事だと思いますので、そこの仕組みづくりをしっかりと今後も行っていただきたいというふうに思います。次に、令和5年度には、子ども食堂マップの展開やオープンデータの公開が行われました。そして、今年度は、その更新、拡充はどのように行われたのか。そしてまた、子ども食堂を必要とする家庭がアクセスしやすくなる仕組みづくりはどのように進められたのか伺います。
子ども企画担当課長 令和6年度においては、9月から10月にかけて子ども食堂活動状況調査を実施し、調査で得られた内容を反映するため、2月にオープンデータを更新、3月に子ども食堂マップのデータを更新いたしました。マップに掲載した子ども食堂数については、79か所増えております。この子ども食堂マップについては、LINEを活用したかながわ子育てパーソナルサポートの中からもアクセスできるようにしたことで、より多くの子育て家庭が近くの子ども食堂を手軽に見つけられるようになりました。加えて、チラシを市町村の子ども・子育て所管課へ配布し、子育て家庭にとって身近な市町村の窓口からも子ども食堂マップの情報を得られるようにいたしました。
石川(裕)委員 子ども食堂マップは私も確認をさせてもらいましたけれども、内容を確認すると、私は川崎市麻生区から選出させていただいていますけれども、麻生区では、このマップの中では登録は3か所になっています。でも、実際には、麻生区にはもっと子ども食堂はあります。そういう中では、まだまだ未登録の事業者が多いと思いますので、必要とする家庭に届くようにするためにも、ぜひこの登録数を増やしていただきたいというふうに思います。次に、令和5年度進学・就職支援として、176人に約575万円の補助が行われました。これは1人当たりにすると3万円程度になりますけれども、今年度、この支援対象者数や支援総額に変化があったのか。そして、進学、就職を希望する若者にどのような変化があり、支援にアクセスできていない若者への施策はどのように講じたのか伺います。
生活困窮者対策担当課長 この事業は、若者を支援するNPOと連携し、生活困窮世帯やヤングケアラーなど、家庭や家族から十分な支援を受けられない者に対し、進学や就職など社会に巣立つための初期費用を支援する事業で、令和6年度は延べ195人の若者に前年度と同額程度の支援を届けることができる見込みです。支援を受けた若者からは、自立に向けたチャンスをいただいた。次は自分が人を支える側になりたいなど、前向きな声をいただいております。若い方は、困難を抱えていても自覚がない。また、どう相談したらいいか分からず、支援につながりにくいことから、これまで生活困窮対策推進本部では、各種LINE相談の窓口立ち上げや、直接学校に出向いて講義を行うなど、若者が支援にアプローチしやすくなるよう工夫を行ってきました。
石川(裕)委員 支援にアクセスが難しいというか、そういう若者に対しての施策というものを、ぜひ講じていっていただきたいと思います。次に、令和5年度、県立学校で女子トイレや保健室への生理用品配備が実施されて、今年度も継続をされています。生徒の利用状況はどのように把握しているのか。そしてまた、生徒や学校側から寄せられた要望や課題を踏まえ、今後の継続の必要性について教育委員会の見解を伺います。
保健体育課長 県教育委員会では、全ての県立学校の女子トイレに生理用品を気兼ねなく利用できるような形で配備しています。中には年度途中で追加購入する学校もあり、有効に活用されていると認識しています。なお、配備等に関する新たな要望はありません。県教育委員会といたしましては、今後も引き続き、生理用品を配備していきたいと考えております。
石川(裕)委員 一応、こういう配備をしていただいた中でいくと、今後も、やはり継続をしていっていただきたいというふうに思います。この質問の最後に知事に伺いますけれども、令和5年度から6年度にかけて、生活困窮者支援から孤独・孤立対策へと政策の軸は移されましたけれども、子ども食堂支援や進学就職支援、生理の貧困対策など、様々な支援策が今展開されたということは伺いました。これらの施策について、その成果や課題をどのように総括しているのか。そしてまた、水光熱をはじめ食料品などの物価高騰が続く中で、支援が必要な人々に適切に届く仕組みの構築など、令和7年度以降、県として目指すべき支援の在り方や具体的な成果目標をどのように想定しているのか、併せて伺います。
黒岩知事 県では、昨年3月に策定した新かながわグランドデザインのプロジェクトの一つに生活困窮を位置づけ、成果目標として、孤独・孤立などに係る指標を掲げ、多様な担い手と連携した取組を進めています。今年度は、官民連携によるかながわつながりネットワークを立ち上げ、NPOなどの支援団体から意見を伺っています。その中では、ライフステージの変化をきっかけに人や社会とのつながりが薄れ、孤独・孤立に陥っていく方が多く、こうした方が緩やかにつながることのできる居場所が必要との意見がありました。また、県内のネットカフェ等を利用する住居不安定者の実態を把握するため、スマートフォンの位置情報により調査した結果、約1,300人の方が月の半分以上、ネットカフェで寝泊まりしていることが分かりました。そこで、県では、孤独・孤立に悩む方が人や社会につながることができる居場所のマップ化や、そうした場所を運営する人材育成のための経費を令和7年度当初予算案に計上しました。また、住居不安定者の自立を後押しするため、新たに生活基盤を立ち上げる際に必要な家具や家電等の購入支援のための経費を計上しています。県では、生活困窮者対策推進本部を中心に、生活困窮者の目線に立ったこうした取組を着実に進めており、今後も多様な担い手と連携しながら、誰もが自分らしく夢や希望を持つことができる優しい社会の実現を目指してまいります。
石川(裕)委員 知事から答弁いただきましたけれども、まず要望を申し上げます。生活困窮者支援が縮小されることなく、必要な支援が継続的に提供されるように求めます。そしてまた、生活困窮者対策推進本部ですけれども、今後の位置づけと役割を明確にしていただいて、積極的に本部を活用して、支援が確実に届く仕組みを構築していただくよう強く要望をいたします。